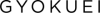EXHIBITION
2019.2.12-20 今井俊満展 TOSHIMITSU IMAI
1969年、日本橋三越本店にて『1952-1969年 今井俊満 滞欧作展』が開催された。この展覧会には1952年の渡仏以来、17年間に渡る今井の作品群が展示された。本展出品作「苔と石」(1968)もその中の一つである。
1960年代、日本におけるアンフォルメル運動はすでに終焉を迎えており、芸術をめぐる国際的な潮流もめまぐるしく変遷していった。芸術によって芸術を問うというあり方に対して、今井は「芸術運動というよりも社会現象の一部」であると批判的な態度を示している。 そのような状況を背景にしつつ、60年代初頭には、パリ、ミラノ、ウィーン、日本、ナポリなどで次々と個展を開催するなどの地道な活動を行った。50年代にはジャクソン・ポロックのドリッピングとの類似を指摘されることがあった彼の画風は、小石やワニスを使用した厚みのあるマチエールへと変化し、60年代後半には、彼の基本的要素である光、自然、行為との統合へ向かっていく。1968年「苔と石」は、今井のアンフォルメル期における集大成として位置づけられる。
1970年代後半、今井はパリのP・ファケッティギャラリーにて二度の個展を開催している。P・ファケッティギャラリーは、ジャン=デュビュッフェ、アデル、フンデルトヴァッサーなど当時の前衛芸術家を育てあげ、またヨーロッパ大陸ではじめてアメリカ抽象表現主義の展覧会を開催したギャラリーである。70年代の今井の作品は、アンフォルメル期と花鳥風月期の過渡期にあり、厚塗りのマチエールは排され、タブロー空間を引き裂くような激しい筆跡が現れるようになる。画面に描かれる諸々の記号(signe)は、パリの批評雑誌において、東洋のカリグラフィー、アラベスク模様と称された。書道や茶道に代表されるように、人間のエネルギーとそれを制限するような形式的側面が共存する当時の作品は、「人間と記号の間の闘争的なシミュラークルのなかで表面を過剰なまでに攻撃する」 と形容された。日本の伝統という自らの根源への遡行は、「Black」(1975)や「Rouge」(1975)などの形式を経て、花鳥風月へと展開していく。